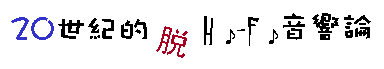
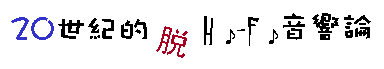
我がオーディオ装置はオーデイオ・マニアが自慢する優秀録音のためではありません(別に悪い録音のマニアではないが。。。)。オーディオ自体その時代の記憶を再生するための装置ということが言えます。面白いことに映像は平面だが、音響はたとえモノラルでも室内音響の助けを借りて3次元で認識・再現されます。ところで20世紀が残した録音にはどういうものがあるだろうか? 以下、概略ながら追ってみました。。。。の前に断って置きたいのは 1)自称「音源マニア」である(ソース保有数はモノラル:ステレオ=1:1です) 2)業務用機材に目がない(自主録音も多少やらかします) 3)メインのスピーカーはシングルコーンが基本で4台を使い分けてます 4)なぜかJBL+AltecのPA用スピーカーをモノラルで組んで悦には入ってます。 5)映画、アニメも大好きである(70年代のテレビまんがに闘志を燃やしてます) という特異な面を持ってますので、その辺は割り引いて閲覧してください。 録音年代順のレビュー我がオーディオ装置はオーデイオ・マニアが自慢する優秀録音のためではありません(別に悪い録音のマニアではないが。。。)。オーディオ自体その時代の記憶を再生するための装置ということが言えます。面白いことに映像は平面だが、音響はたとえモノラルでも室内音響の助けを借りて3次元で認識・再現されます。ところで20世紀が残した録音にはどういうものがあるだろうか? 以下、概略ながら追ってみました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【1960〜1970年代】 録音環境 この時代には50年代には各社のローカル・ルールで行っていた録音規準がRIAAによって統一され、電蓄に代わってコンソール型のステレオが高級家電として一般家庭に入る頃です。ポップスでマルチ録音によって未知の電子音響が模索されたり、新しいマルチ・チャンネル再生のフォーマットの開発など、エレクトロニクス技術が進歩的で華々しい時期です。一方でポップ・カルチャーに代表されるように文化全体がチープなスタイルになるのもこの時代の特長です。しかし横綱だけが相撲ではなく、ホームランだけが野球ではありません。これまでの録音でも小市民的な音楽嗜好はあるのですが、これがメディアに前面に出るようになったのが60年代的な出来事だったように思います。
再生機器
ページ最初へ 【1980年以降】 録音環境 この頃の画期的な出来事はPCM方式によるデジタル録音が可能になったことです。ワウフラッター=ゼロ、ノイズレスで全領域で均等な90dBのダイナミックレンジを誇る録音が可能になりました。しかしデジタル特有の小音量での量子化歪みや、初期のアナログ・フィルターの強烈な位相特性の悪さなど手伝って、船出は必ずしも順調ではありませんでしたが、徐々に録音側での演算ビットの増加やデジタル・フィルターの組込みなどの改良を経て90年代にはLPの存在を凌駕するようになりました。また録音の品質管理が圧倒的に楽になり、個人レーベルで質の高い録音が出るようになります。ダビングによる音の劣化が少ないことや音程とリズムを別々に制御・変換できるテクノロジーを武器に、Fairlight社に代表されるようなシーケンサーやサンプラーによるコンピューター・ミュージックが生まれたのもこの時期です。一方でアコーステッィク楽器だけのアンプラグド・コンサートも流行るなど、音楽そのもののを人間のパーソナリティに留めておこうとする努力も続けられることになります。
再生機器 一般にデジタルvsアナログの議論は尽きないものの、もともとアナログ・テープには高域エネルギーの磁気飽和からくる圧縮作用(テープ・コンプレッション)があり、それが大音量時にソフトな歪みを伴う柔らかい音を演出していたのですが、ほとんどのHi-Fi装置は逆に高域特性を上げることで明晰さを演出してました。80年代にワイドレンジと称して多く製造された国産3wayブックシェルフのほとんどは、スコーカー領域のトランジェットが弱くさらにこの傾向に輪を掛けていたようです。結局こういうところにデジタル録音を持ち込むと、ほとんど聞こえないはずの高域の過度特性が膨らみ過ぎて、知らず知らずに聴覚を刺激する不快な音になるのです。 ほとんどの人はデジタル録音そのものの性能が劣っていると感じたようですが、一部そういう面もあったにせよ、買った機材よりCDソフトのほうが安いことへの単なる八つ当たりも含まれていると考えられます。実際は単なる相性の問題で、真空管のように高域をソフト・ディストーションで対処する機材を加えることで多少とも緩和できるものです。それでも低域から高域のトランジェットが均一なスピーカーの存在は不可欠であり、その解答のひとつがフルレンジ・スピーカーなのです。私の場合は真空管のバッファー・アンプとパワー・アンプでフルレンジ・スピーカーを鳴らすようにしています。 もうひとつの文化的傾向としてPCM音源によるコンピューター・ミュージックの流入ですが、80年代初頭ではFairlight社のシーケンサーを初め、ダイナミック・レンジの少ない8bit音源なども多かったこともひとつの問題をはらんでいます。もっともミキシングはアナログをベースに行われたので、高域にアクセントをもたせた音はマスターテープの劣化とともに輝きが損なわれるもので、70年代のアナログ・シンセほどではないにせよ厄介な代物です。特にテクノ関連では70年代初頭に続いて第二の黄金期ともいえる作品が目白押しで、オリジナル・テープそのものが作品といえるこれらの作品はそのまま再生すればオリジナル通りなのかという疑問はずっと付き纏います。そういう評価についてはコンピューターでの音楽製作の知識がなければ判らない部分が多く、今後の課題ということになりそうです。同時に日本のポップ・ミュージックの評価にも繋がっていくものと思います。 ページ最初へ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
オーディオの歴史80年の邂逅。見栄えも大事かな?
参考リンク
主に利用している店です。
口コミで評判の良い製品をネットで安く買うのもいいですが
やはり脚を使って実物を聴いたほうが自分の好きな物に出会えます。
オーディオをゆっくり安心して選べる店というのも少ないので関東近辺の方は参考にどうぞ。
ハイエンド・オーディオ
オンケン オーディオ:富士通テン TD512(スピーカー)を購入するときお世話になりました
SIS:Beard Audio BB100(ステレオアンプ:中古品)を購入するときにお世話になりました
レコーディング用機材
Junction Music:Oram Hi-Def 35 (パラメトリックEQ)を購入するときにお世話になりました
サウンドハウス:Digitech VTP-1(マイクプリ)、Lexicon MPX100(エフェクター)、RANE MP2016(DJミキサー)など
ネットでレコーディング機材を購入するときに利用しています
キット・部品
コイズミ無線:パイオニア PE-16M+スピーカーBOXを購入するときにお世話になりました
ヒノ・オーディオ:Fostex R100T(スピーカー用アッテネータ)を購入するときにお世話になりました
トライスタージャパン:スピーカー・ケーブル、セレクターなどのネットで小物類を購入するときに利用しています
ビンテージ・オーディオ
エイフル:JBL D130+米松箱(スピーカー)を購入するときにお世話になりました
音の市:Altec 802C+511B(ホーン)、JBL N1200(ネットワーク)を購入するときにお世話になりました
アポロ電子:Motiograph MA-7515(モノラル・アンプ)を購入するときにお世話になりました